トップページ > 診療科・部門 > 部門 > 糖尿病総合診療センター > スタッフ紹介
スタッフ紹介
専門医からのコメント
・糖尿病内分泌代謝科 梶尾裕(糖尿病総合診療センター センター長)
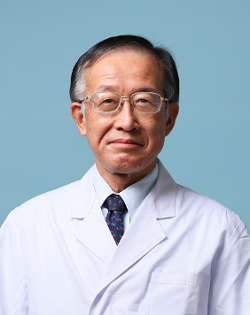
糖尿病は、多くの診療科や部門と協力して一人一人の患者さんにきめ細かい医療の提供が必要な疾患です。また、かかりつけの先生方との協力も欠かせません。糖尿病は、糖尿病内分泌代謝科が専門分野として扱っていますが、関係者で協力した医療の提供がますます重要になってきています。
当センター病院がより一体となって、かかりつけの先生からのご紹介や患者さんの受け入れをよりスムーズに行い、充実した総合診療をこれまで以上に進めていくために、今回、糖尿病総合診療センターを設立いたしました。
皆さんの期待に応え、より適切な医療を提供するために、糖尿病研究センターや糖尿病情報センターとともに、臨床研究もさらに積極的にすすめてまいります。
当センター病院は、糖尿病総合診療センターを中心として、これまで以上に糖尿病の総合的、先進的医療に全力で当たります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
・糖尿病内分泌代謝科 坊内良太郎(糖尿病総合診療センター 副センター長)

糖尿病総合診療センターは、国立国際医療研究センターの重要なミッションの一つである糖尿病の診療・研究の発展、若手医師の育成を目指して設立されました。近隣の医療施設の皆様、研究所糖尿病研究センターの研究者と密に連携し、糖尿病診療の充実、糖尿病学の進歩のために努めてまいります。
糖尿病合併症を診療する専門医からのコメント
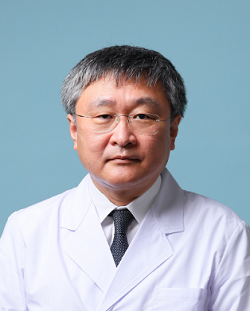
循環器内科は糖尿病、高血圧、脂質異常症、喫煙、肥満などの危険因子が相乗的に起こす動脈硬化による冠動脈疾患と末梢動脈疾患の診断と治療を行います。 生命、QOLに関わるので、早期発見、早期治療が重要です。

本邦では糖尿病網膜症で年間約3000人が失明しています。失明を予防するためには早期発見と病態に応じた薬物・手術治療が必要になりますが、血糖のコントロールが最も重要で、糖尿病通院歴が10年以上ありここ数年のHbA1c値が8%以上で眼科を受診したことがない場合は、自覚症状がなくても網膜症が進行している可能性がありますので早めに眼科を受診するように勧めてください。
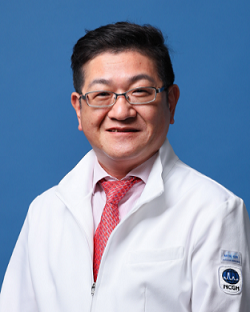
腎臓は血糖の影響を受けやすく、糖尿病性腎症は透析導入第1位の疾患です。当科では身体的のみならず、社会・心理面も含めた治療を心掛け、看護師、薬剤師、栄養士、臨床工学技士などとチーム医療を推進しています。
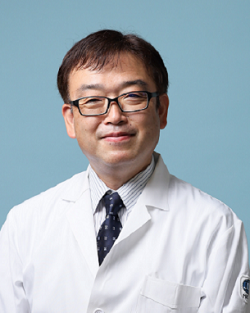
神経生理検査として神経伝導検査を行っており,糖尿病性末梢神経障害が疑われる患者さんの評価が可能です。脳卒中センターにて脳卒中診療も積極的に行っており,多職種で専門的な診療をお受けいただけます。

糖尿病の皮膚病変は、①発見契機となるもの、②合併・悪化しやすいもの、③予後・QOLに関るものに大別されます。②で多いのが蜂窩織炎で、随時入院をお受けします。また糖尿病性足病変は③で最重要で、FCC(Foot Care & Cure)という多診療科/職種による診療で取り組んでいます。局所陰圧閉鎖処置や多血小板血漿処置も行っています。

歯周炎が糖尿病を悪化させ、また歯周炎の改善が糖尿病の病状改善につながることがわかってきています。糖尿病の治療には食事等生活習慣全般の見直しのほか、歯科での歯周治療や口腔清掃の習慣付けも必須です。
関連診療科の専門医からのコメント
当院の人間ドックセンターは疾患の早期発見や予防を積極的に進めています。糖尿病が発見された場合、糖尿病総合診療センターへご紹介し、迅速に精密検査と高度かつ専門的な治療を受けていただいています。
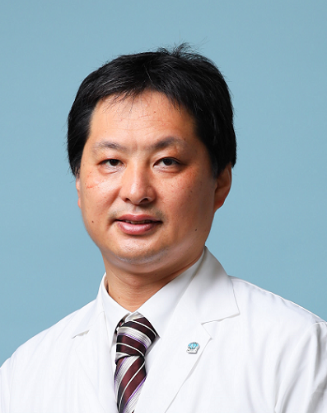
救急科は、救急車による搬送患者さんの初期診療に24時間365日携わります。糖尿病やその合併症が原因で具合が悪くなった際に、時間外でも専門医と連携を取って診療しておりますので安心して依頼されてください。

糖尿病教育入院症例への運動指導を行なっています。また、さまざまな科に糖尿病の患者さんはおられ、合併症の神経障害、循環障害、足変形や歩行障害、潰瘍への対応も、関連各科と協力して行なっています。
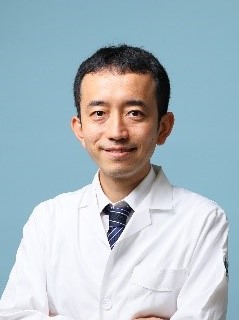
総合診療科では、医学面だけではなく心理面、社会面を包括したケアを外来および入院で提供します。糖尿病以外にも困難を抱える患者さんが、自分らしい生活を維持できるよう支援いたします。糖尿病の患者さんが感染症等に罹った際に、院内の他部門と連携して最善の治療を提供します。
消化器内科では糖尿病代謝内科との連携診療が欠かせません。内視鏡手術や化学療法中でも血糖管理は重要です。また、脂肪肝や膵癌は糖尿病と密接にかかわっており、双方向での診断や治療について密に連携して管理治療を行っています。
食道癌の手術では周術期にステロイドを使用したり、手術の侵襲が高いので、多くの場合、術後の血糖は上昇します。血糖が上昇したままにしておくと、感染性合併症(肺炎や縫合不全など)が増えることがわかっています。ICUや病棟では多職種が連携して、周術期の血糖測定を厳密に行い、合併症の軽減に努めています。安心して治療を受けてください。
糖尿病の急激な悪化の背景に膵臓の腫瘍性疾患が隠れていることがあり、糖尿病代謝内科と連携して診療にあたっております。また、外科手術、特に代謝臓器である肝臓や膵臓の手術の周術期には、糖代謝を含めて大きく代謝能が変化することから、密に協力して慎重な周術期管理を行なっております。さらに、膵臓手術後は一定頻度で糖尿病発症のリスクがあることから、長期にわたって患者様をフォローする体制も整っております。膵島移植の実施施設でもありますので、関心のある患者様がございましたらご紹介ください。

糖尿病合併妊娠、妊娠糖尿病などの周産期管理にあたり糖尿病総合診療センターとの連携を密にとっております。また女性のヘルスケアを考える上で、妊娠糖尿病を罹患された方、多嚢胞性卵巣症候群などの月経不順があった方は、更年期以降に糖尿病を発症するリスクが高く、早期からの介入が望まれます。糖尿病は婦人科では子宮内膜癌のリスクファクターとしても知られており、子宮内膜癌の併存疾患として適切な管理が必要となります。
関連部門のスタッフからのコメント
看護職員は、教育入院をはじめ、フットケア、インスリン注射や血糖自己測定、持続血糖測定(CGM)・インスリンポンプの導入、糖尿病透析予防指導などの支援を行っています。また、多職種と連携し患者さんのライフスタイルに合わせた治療の提案などに、糖尿病看護認定看護師、糖尿病療養指導士などが活躍しています。

私たち薬剤師は、最新のエビデンスを踏まえた指導を患者さんやご家族・支援者に行うことで薬の特徴や副作用、生活上の注意点等への理解を支援します。また、多職種と協力して安全で継続可能な薬物治療を検討します。
糖尿病と臨床検査は密接な関係にあります。採血や血糖検査・心電図など多くの検査に関わっています。今後は糖尿病教室などでも糖尿病総合診療センターの一員として、患者さんに寄り添った臨床検査を提供して参ります。
糖尿病患者さん個々の症状に合わせて管理栄養士が治療効果の上がる個人栄養食事指導を実施しております。(※ご家庭で調理を担当されるご家族とご一緒に受けて頂くと効果的です。)
また、栄養状態に問題がある場合には多職種(医師、歯科医師、看護師、薬剤師、検査技師、管理栄養士等)連携して栄養サポートしております。 退院後、外来診察時に栄養食事指導を実施し食事療法を継続しております。